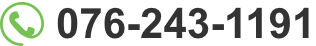診療科・部門のご案内Clinical Departments Information
整形外科
整形外科の特徴
整形外科は運動器(骨・関節・筋腱・神経)における病気や怪我を治療する診療科です。
整形外科に来院される患者さんは日常生活動作が全て制限されるような全身症状があることは少なく、特定の動作や姿勢で痛み(症状)が出てくる場合が多いことも特徴です。結果である痛み(症状)の治療も大切ですが、「何故その痛み(症状)が出てくるのか?」という原因の追求とその治療が重要となります。内服薬や湿布薬、注射だけで解決しない場合が多いのもそのためであり、痛い場所だけではなく、一見つながりのないように思える他の場所に問題が見つかることも少なくありません。人間の身体はつながっています。ある関節の動きには必ずその他の関節の動きが伴ってきます。その流れの中のどの部分に障害が起こっても、障害は起こりえます。
例えば腰の痛い患者さんがいたとします。レントゲンでは確かに加齢性の変化(脊椎症性変化)があり、「変形していますね」と言われるような状態だったりしますが、下肢の筋緊張性の増加(柔軟性の欠如)があり、腰の負担が増えているための腰痛であったりします。そのような場合にはリハビリで姿勢の重要性とストレッチなどの自主トレーニングを指導してもらい、それを実施することで痛みが軽減してくる可能性があります。そのような意味でも私達はリハビリテーション(リハビリ)を重要視しており、リハビリスタッフと連携して日々の診療を行なっております。
当科の方針
内服薬や外用薬、注射、さらには手術が必要なことも多々ありますが、基本的に痛み(症状)が治るためには患者さん本人の治癒能力が重要であり、あくまで治療の主体は患者さん本人と考え、診療にあたっています。一連の診察の中で、診断をつけることを目的とするのではなく、「どうやったらこの痛み(症状)を解決できるのか?」、その解決方法を患者さんと一緒に考えられたら理想的ではないかと考えています。診察室でのコミュニケーションを大切にし、実際に触って、動かして、さらに超音波診断装置も駆使しながらの診療になりますので、診察に時間がかかります。1日に診察できる患者さんの数にも限度がありますので予約制となっておりますことをご了承ください。
また予約制にしてもなお、沢山の待ち時間が発生していることも大変心苦しく思っております。真摯に診療に取り組んでいる結果なのですが、こちらもご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。また下記に挙げるような得意分野以外の疾病の治療が必要と考えられる場合には、金沢大学整形外科とも提携しており、ネットワークを生かしてより専門的な治療が受けられる病院・専門医への紹介も責任を持って行なっております
得意とする診療分野
スポーツ障害・外傷
スポーツをこよなく愛する選手からレクリエーション・レベルにあるスポーツ愛好家まで、スポーツ活動においていろんな痛みや障害を抱える方が対象です。そのような方であれば年齢は問いません。痛みを軽減し、リハビリと連携しながら障害予防、パフォーマンス・アップを目指します。
膝関節外科
膝関節靭帯損傷、膝半月板損傷、膝蓋骨脱臼などの外傷から、変形性膝関節症などに代表される変性疾患に至るまで、リハビリを中心とした保存療法を大切にしながらも関節温存手術を目的として関節鏡を駆使した靭帯再建術、半月板縫合術やより高度な膝関節周囲骨切り術も数多く取り組んでおります。また関節温存が望めない場合に人工関節置換術も行なっており、膝関節に関わる全ての手術に対応できます。
関節鏡手術(肩関節・肘関節・股関節・足関節)
膝関節だけではなく肩関節・肘関節・股関節・足関節に至るまで最小侵襲手術である関節鏡を駆使した関節鏡手術が行える北陸でも数少ない病院の一つです。
新たな取り組み
胸腰椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折の患者さんに対する多職種連携アプローチ
多忙な業務の中でも、胸腰椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折の患者さんの救急搬送依頼をなるべく断ることなく受け入れ、よりスムーズに治療開始が可能となるように当院内科医師が主治医となり、そこに整形外科医,麻酔科医、病棟ナース、薬剤師、理学療法士等といった多職種が連携して関わることができるようにしています。骨折の背景にある高齢者特有の様々な合併症のリスクを低減する可能性が高い画期的なアプローチです。
医師紹介

整形外科部長 島 洋祐
| 氏名 | 島 洋祐(しま ようすけ) |
|---|---|
| 出身大学 | 金沢大学 |
| 認定・専門資格 |
日本整形外科学会専門医 日本スポーツ協会公認スポーツドクター 日本サッカー協会公認C級コーチ 日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ医 |
| 所属学会 |
日本整形外科学会 日本膝関節学会 日本スポーツ整形外科学会 代議員 日本臨床スポーツ医学会 日本 Knee Osteotomy and Joint Preservation 研究会 日本肩関節学会 日本足の外科学会 |
| 自己紹介 |
スポーツ傷害の“Prevention(予防)” 膝関節機能の“温存” この2本の柱をテーマに日々取り組んでいます。 |

整形外科医長 石田 善浩
| 氏名 | 石田 善浩(いしだ よしひろ) |
|---|---|
| 出身大学 | 鳥取大学 |
| 認定・専門資格 |
AO Trauma Basic Principle Couse 修了 骨折治療学会ベーシックコース修了 JATECプロバイダー ACLS EPプロバイダー JMECC(日本内科学会認定救急コース)修了 ISLS(脳卒中初期診療コース)修了 日本ボクシングコミッション コミッションドクター 日本スポーツ協会公認スポーツドクター |
| 所属学会 |
日本整形外科学会 日本スポーツ整形外科学会 日本臨床スポーツ医学会 日本整形外科超音波学会 日本Knee Osteotomy and joint Preservation研究会 日本骨折治療学会 中部日本整形外科災害外科学会 |
| 自己紹介 |
整形外科一般とスポーツ診療を専門に、分かりやすい説明と安心、安全の医療を心がけています。 分からないことがあれば何でも気軽にお尋ね下さい。 |

整形外科医師 前田 麟
| 氏名 | 前田 麟(まえだ りん) |
|---|---|
| 出身大学 | 金沢大学 |
| 認定・専門資格 |
日本整形外科学会専門医 |
| 所属学会 |
日本整形外科学会 日本人工関節学会 日本股関節学会 日本骨折治療学会 中部日本整形外科災害外科学会 |
| 自己紹介 |
股関節疾患を専門に、皆様の痛みに寄り添った丁寧な診療を行っています。 |
外来担当医表
●診療時間 9:00~12:00 14:00~17:00
・初診・再診ともに完全予約制です。必ず事前予約が必要です。
整形外科外来にお問い合わせ下さい。予約は電話でも受付できます。
・月、水、金曜日の午後は、膝肩関節・スポーツ専門外来です。
・お薬を希望される場合は、担当医の診察日を参考にお越し下さい。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 島/石田 |
島 | 島/石田 |
金大Dr |
島/石田 |
| 午後 | 14:00~島/石田 (膝 肩関節・スポーツ専門外来) |
手術 |
14:00~島/石田 (膝 肩関節・スポーツ専門外来) |
手術 | 14:00~島/石田 (膝 肩関節・スポーツ専門外来) |
【午前】
受付時間は8:30~12:00です。診療時間は9:00~12:00です。
予約の方は各時間帯に来院された方から順に診察いたします。時間帯をお間違えなくお越しください。
【午後】
午後の診察につきましては上記の表を参照して下さい。
午後の診療は手術・検査のため遅れたり、あるいは行われないこともあります。
※12/5(金)、12/15(月)~12/22(月)、12/26(金) 島部長 休診です。
※12/26(金)午後 石田医長 休診です。